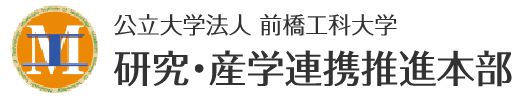ものづくり技術
環境共生的な持続型都市/都市再編•地域再生/産業空間の都市機能への変遷等
環境と人の相互連鎖のなかでどのように生存の場を獲得し、その集積としての都市を創造し、多様な関係性を保ち持続していけるのか?という人類の根源な主題とむきあい、先達の思想や社会背景や現代的課題等を踏まえ、実践的な立場から研究します。
ものづくりと地域づくりの探究
人間の生活環境には、その場所に根付いた生活や仕事、つまりその地域で生活していくための産業があります。しかし、その地域の出身者だけが担い手であるとは限りません。当研究室では、「人間の生活」と「地域の産業」の関係に着目したデザインの実践として、プロダクトの提案や地域社会に寄与する研究を行っていきます。
現代日本における地域の空間デザイン、新たな地域課題に応える場所や空間の提案
建築などの具体的な形があるものと、それらを人と関係づけているの空間や環境について思考し、今までの常識に囚われない新しいデザインとして提案しています。実際の建築設計や空間デザイン、まちづくりの活動、などを行いながら、実践と思考のフィードバックによって生まれる発見的なクリエイティヴィティを社会に還元することを目指します。
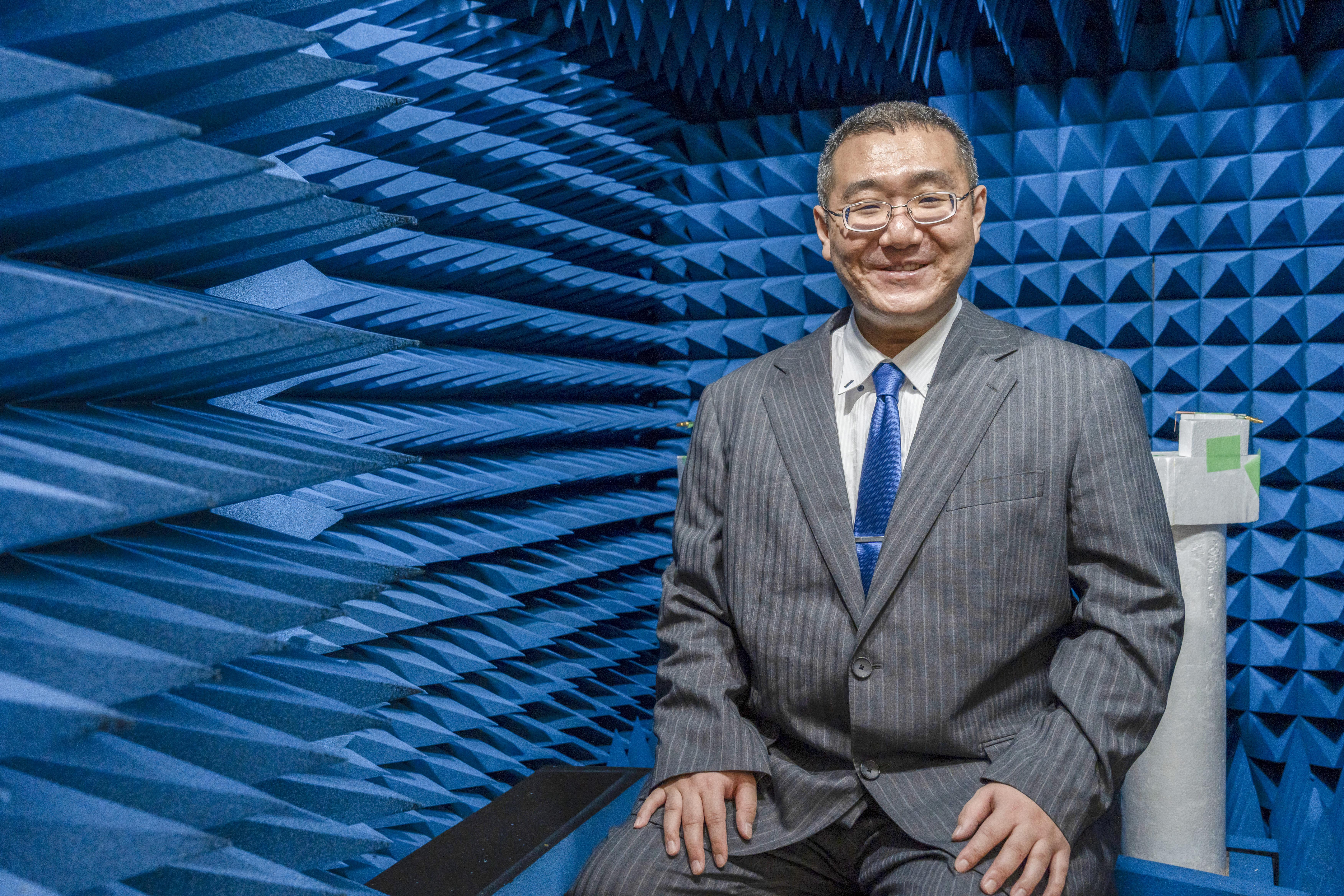
あらゆるモノがインターネットでつながる時代に必要なアンテナの実現に関する研究
電磁波工学研究室では、身近なスマホや医療デバイスに使われる「見えない電波に関する技術」を、自ら設計・製作・測定しながら研究できる実践型の環境を整えています。教科書に載っている基本的なアンテナから導電性繊維による最新ウェアラブル技術まで、手を動かして理解できるのが強みです。将来は、安心・安全でワイヤレスが当たり前の社会を、あなたの技術で支えるエンジニアへと成長することを目指します。
赤外線分光カメラ撮像データの解析
リモートセンシング装置を開発して人工衛星や惑星探査機に搭載し、対象の遠隔観測を行って科学成果を挙げます。近年では、小惑星探査機はやぶさ2に搭載した中間赤外カメラTIRをJAXAと共同で開発して、小惑星リュウグウを観測して地球の水や生命誕生の秘密を探るためのデータを取得しました。さらに、TIRの後継機であるTIRIを二重小惑星探査機Heraに搭載して、小惑星DidymosとDimorphos系の探査を行う予定です。開発した赤外分光カメラを惑星探査だけでなく、医療に活用できないか、模索しています。
歴史的建築に関する調査研究
歴史的価値を持ち始めたモダニズム建築や近代化遺産の魅力を発信し、現代のライフスタイルに適した利活用についても提案しています。研究で得られた知見について、広く社会に還元するべく、建築史の面白さを共有するための展覧会開催や、十分に認知されていない歴史的建築の魅力を発信するライティングプロジェクトなどを実施しています。
ルドルフ・シュタイナーの建築と思想に関する研究
研究とものづくりは表裏一体です。ドイツ建築論の文献研究、近代建築の作家研究を進める一方、大学発べンチャーである㈲ビオ・ハウス・ジャパン一級建築士事務所での設計活動をとおして、健康と環境に配慮した住まい(バウビオロギー建築)の普及を目指しています。
対人支援ロボットに関する研究
本研究室では装着型アシストロボットスーツの開発、対人移動支援ロボット、自律移動ロボットの開発、脳波によるパワーアシスト技術の開発の4つのテーマを研究しております。ロボット技術を用いて社会問題となっている人手不足の解消や負担軽減に貢献できることを目指しています。
鉄筋コンクリート構造物の品質確保/維持管理、品質確保システム、高強度/高耐久コンクリート
我が国で深刻な社会問題になっている鉄筋コンクリート(RC)構造物の老朽化対策に取り組みます。具体的には、既設RC構造物の劣化診断、機能性塗料を利用したコンクリートの変状モニタリング、新設RC構造物の高耐久化を目指した産官学の協働システム、超高強度/超高耐久コンクリートパネルを用いた恒久的な補修工法の開発等が近年のテーマです。コンクリート材料の高性能化/高機能化を通して安全・快適な社会の実現に貢献します。
ニューメディア・インストール史
アート/デザインの展示・鑑賞体験は、ニューメディアの導入によって近年ますます多様なものとなっています。歴史を参照し、ニューメディアが発明され普及する(インストールされる)過程において、ひとびとの振る舞いや認識がどのように変化してきたかを読み解く当該研究は、まだ知られていないテクノロジーの可能性を予見する意味で大変重要なこころみであると考えています。
建築構造部材の耐震設計法に関する研究
地震大国日本おいて、建築構造物の耐震安全性を確保するために、また、省資源や施工性の観点から経済的および力学的に材料を適材適所に配置することにより,優れた性能をもつ新しい建築構造を実験的手法を用いて開発しています。人々の暮らしが地震等の自然災害よって脅かされない世の中が実現できることを目標にし,日々研究に励んでいます。
ロバスト性・冗長性に優れた建物および都市の構築
地震大国である日本では構造工学の発展が日々の安心・安全を支えています。そこで、生命・財産・文化の保全、都市機能の維持、環境負荷の低減を目指した構造工学理論を発展させるため、建物の力学挙動を把握し、先端的な建築構造の実現を目標に研究を行っています。
都市と建築の関係性についての研究
建築を軸に空間の在り方を広く考察し、これからの社会の姿とそれを支える建築の新しいカタチについて研究します。また地域と緊密に連携し、その成果と知見を社会実装することを目指します。
住宅・建築物の熱・湿気・空気環境と省エネルギーに関する研究
住宅やオフィスビルなどにおける室内の暑さや寒さの問題、梅雨期・夏期の高湿度と冬期の過乾燥の問題、PM2.5などによる空気汚染といった室内環境の研究に取り組んでいる他、建物外皮の断熱・気密化、太陽光・太陽熱といった自然エネルギー利用など、建築物の省エネルギーについて研究しています。研究を通じて「省エネ」で「快適」、かつ「健康」な住環境の実現を目指します。
建物及び都市の長寿命化に関する研究
研究対象は、建物だけでなく「ひと」と「とき」。長期的な視点から質の高い建物を建て丁寧に使う仕組みを実装することで、地域や都市の持続可能性を高める社会システムの構築を目指して、建築に対する既存概念にとらわれず様々な人や分野と連携して研究を行います。
次世代モビリティの開発・高齢者向け製品の開発
プロダクトデザイン研究室では、社会が求める大きな変革に応えるために、デザインコンセプトの創出からその具現化までを一貫して担うプロダクトデザイナーの役割を探求しています。モノの造形にとどまらず、サービスやシステムと統合された新たな価値提案の実現に向けた研究に取り組んでいます。
鉄筋コンクリート造部材の構造性能・ハーフプレキャスト梁における水平接合面のせん断摩擦性能に関する研究
持続可能な社会の実現が求められています。世界共通の課題・日本ならではの課題に,環境配慮型材料やプレキャスト構造等で対応することに備え,これらの採用が部材の構造性能に及ぼす影響などについて研究しています。

建築意匠・設計に関する研究
建築の現場で得られた経験と知識、建築情報を大学教育に還元し、学生に建築論、設計理論、技術、職能論、倫理観などを学ぶ機会を与え、社会への接点を見出し、創造のための場
- 1