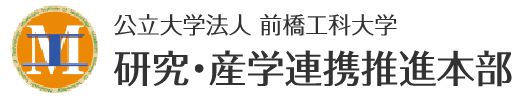ロバスト性・冗長性に優れた建物および都市の構築
地震大国である日本では構造工学の発展が日々の安心・安全を支えています。そこで、生命・財産・文化の保全、都市機能の維持、環境負荷の低減を目指した構造工学理論を発展させるため、建物の力学挙動を把握し、先端的な建築構造の実現を目標に研究を行っています。
主な研究成果
構造物の地震応答解析における減衰は、減衰比が周波数に依存しないこと、極めて固有周波数が高い高次モードは地震応答に関与しないことが前提となっています。研究においても実務においても、レイリー減衰に代表される比例減衰が一般的に採用されています。レイリー減衰は、質量比例項と剛性比例項の線形結合として表されるもので、系の質量と剛性に応じた減衰を設定でき、自由度の大きな系でも計算効率が良く、弾性域では、広い振動数域で計算結果を実測値に一致させられる等の特徴があります。しかし、系が降伏するなどし、剛性とともに固有振動数や固有モードが変動すれば、レイリー減衰は減衰力を大きく見積もりすぎる懸念が従来より指摘されています。そこで私たちは、建物の非線形地震応答を適切に評価できる減衰モデルの開発を目指し、振動解析で提案される種々の減衰モデルについて、構造物の弾塑性応答に対する適性を比較、検討しました。応答解析の結果より、レイリー減衰は系が降伏したときの減衰力を過大評価する傾向が、Menegotto-Pinto型の履歴モデルよりBilinear型でより顕著なこと、また、等価減衰比の代表値であるζeqと減衰エネルギーに強い相関があること、などを明らかにしました。
どのような産学官連携ができるか
⽇本各地で⼤規模地震が多発しており、住宅倒壊や多数の避難者が発⽣しています。また、南海トラフ域での大地震について近い将来の発⽣の切迫性が指摘されています。都道府県や市町村における、住宅・建築物の耐震化の実態分析や、耐震化による被害軽減効果の分析を⾏うことで、地域防災計画や耐震改修促進計画の⾒直しを⽀援することが可能です。
⾃治体の減災計画では被害半減以上を⽬標とする場合が多いですが、例えば住宅の耐震化率が95%を達成した場合、被害がどの程度軽減するかなどを試算することができます。これまでの幾つかの自治体に対して計算した結果、被害軽減効果は4〜8割減となり、概ね被害半減以上の効果を確認しています。
多くの都府県の市町村の耐震計画では、重点的に耐震化すべき地区を設定し、対策を優先的に実施する例が見られます。地区別の被害想定結果を利⽤して、耐震化による減災効果の⾼い地区を順位付けし、重点地区を設定することなどが可能です。
SDGs該当番号