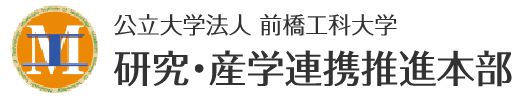ライフサイエンス
人体機能構造学を基盤とする情動機能の機構解明と計測方法の開発
情動感性生理学研究室ではヒトのこころに関した基礎研究や人体の解剖学的・生理学的特性を考慮したヒューマン側インターフェース作りのための基礎研究をしています。そのため必要に応じ、被験者協力実験や生体現象の深部機構を探るためのモデル動物実験をしています。
生物の感覚―運動メカニズムの解明とその工学的再現・産業応用に関する研究
昆虫を中心とした動物の運動や行動のしくみを、「脳・神経系」、「身体の構造」、「生物を取り巻く環境」の三点から解明し、「生物らしい動き」を機械で再現することを目指して研究を行っています。生物学の知見を新しいものづくりに結び付け、環境に適応できる機械、そしてヒトと調和できる機械を創造します。
環境とヒト健康に関わる微生物の研究
ヒトの健康と環境浄化に役立つ微生物の研究を行っています。ヒトの腸内には多数の細菌が生息しています。ヒトの腸内より分離した細菌の機能解析、健康に役立つ乳酸菌の探索を行い、ヒトの健康増進を目指す研究を行なっています。さらに、微生物を使用した環境浄化の研究も行っています。また、食品廃棄物を原料として使用し微生物の発酵によりクリーンなエネルギーである水素およびエタノール生産を行う研究も行っています。
対人支援ロボットに関する研究
本研究室では装着型アシストロボットスーツの開発、対人移動支援ロボット、自律移動ロボットの開発、脳波によるパワーアシスト技術の開発の4つのテーマを研究しております。ロボット技術を用いて社会問題となっている人手不足の解消や負担軽減に貢献できることを目指しています。
蛍光による光診断、光線力学療法、光熱療法に関する研究
可視光より波長が長い光は見えませんが、専用センサによって身体の中を傷つけずに見たり、治療することができるかもしれません。量子ドットという特殊な色素をネズミに注射すると、大脳皮質の血管が見えたことから新しい血管造影法につながる可能性があります。生体適合性が十分に検討されていないものも少なくないですが、人体構造を忠実に再現したモデルの数値解析により、その診断や治療の有効性を検討することができます。
ヒトの認知的特性・身体的特性の解明に関する研究
人に優しいデザインとは、一体どのようなものでしょうか?この問に答えるためには、“ヒト”という動物の特性、つまり、人間特性を理解する必要があります。本研究室では、ヒトを対象とした実験研究を行うことで人間特性を解明し、ヒトに寄り添ったデザインの実現を目指しています。
農産廃棄物・未利用物の有効活用・機能性評価
農産物の廃棄部位や未利用部位の有効利用法を開発することを目的として、生体に対する有効成分の探索やその機能性評価、新規利用法、高付加価値化につながる技術開発を行っています。また、樹木の保全管理に役立てるための電気計測による非破壊計測・評価法の開発にも取り組んでいます。
連合性長期記憶に関する研究
人体の中でも未解明なことが多い脳。特に当研究室では記憶の謎に迫ります。特に脳の可塑性についての研究を行います。また、得られた知見【脳の可塑的な特性】を用いる事で医療・福祉分野に還元することも目指していきます。
医療・福祉のための計測技術に関する研究
本研究室では、機能性材料・電子回路・信号処理・機械学習等の技術を統合して、生体から発する様々な情報を計測する手法を研究します。特に人間の触覚を再現できる触覚センサを開発して、乳がんの早期発見を始め医療診断、健康モニタリングや、義手の制御などの福祉機器、また介護ロボットへの応用に取り組みます。人々の健康および生活の質QoLの向上に貢献することを目指します。
細胞認識シングル-ストランドDNAプローブを修飾したスクリーンプリント電極によるがん細胞のセンシング
生物の体内では様々な情報が伝達され、それらの伝達には種々の生体分子が関与しています。当研究室ではタンパク質、ペプチド、糖鎖、そして細胞における相互作用を使った分析手法を開発することで、私たちの健康を担う研究を進めています。
遺伝子疾患発症の解明
生物を構成する細胞の中ではたくさんのタンパク質がその役割をはたしています。タンパク質の設計図である遺伝子の異常は病気の発症原因となります。当研究室ではそれらの病気について発症メカニズムを突き止めるとともに、治療薬として役に立つタンパク質医薬品の開発を目指しています。
難消化性多糖の免疫疾患に及ぼす効果と作用分子機序の解明
遺伝子の変異により起こる免疫疾患の骨や小腸、皮膚の機能に与える影響を解明するとともに、それぞれの器官の関連性を検討しています。同時に食品を始めたとして機能性分子を使用して、症状改善の効果を分子メカニズムから検討しています。また、群馬の特産物から新しい高付加価値材料を創製する研究を行っています。一つとして、ブタ由来のコラーゲンから発見された新しい特性を利用して細胞への応用が可能な材料の成形技術について研究を進めています。
ゲノム、エピゲノムに関する技術開発
細胞はゲノムに生物としての情報を、DNAメチル化などのエピゲノムに細胞としての役割や環境への応答の情報を記録するが、これらの情報の異常はがんをはじめとする生活習慣病にも関わることから注目されている。当研究室ではゲノムおよびエピゲノムについて、異常の解析方法の開発、異常を起こす化学物質の探索系の構築、データマイニングなどに取り組み、人々の健康な生活に貢献することを目指している。
刺しゅう式静電容量型体圧・距離センサを用いた介護技能評価システムの開発
本研究においては介護技能を定量的に評価することを目的として、導電性繊維を用いた自己容量型の体圧・距離センサを用いたシステムを開発した。本システムで開発した体圧・距離センサは、導電性の刺しゅう糸を用いた20チャネルの自己容量型のセンサアレイであり、車いすの座面や介護ベッドのマット上に設置することで被介護者の着座位置や着座速度が計測できる。現在、本システムを用いて介護初心者と介護熟練者の介護動作を解析することで介護技能の評価法確立を目指している。
- 1