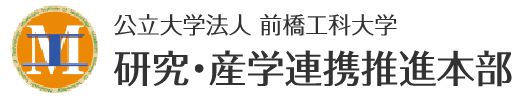情報通信
生体分子の形や動きを理論的に解明する研究
細胞内は膨大な生体分子が高濃度に共存しており、満員のプールのような混雑状態になっています。そのような複雑かつ混雑な環境で蛋白質などの生体分子がいかに運動し、機能を発現しているかは生命科学の大きな謎です。当研究室では、細胞内の生命現象を、生体分子の立体構造や相互作用およびダイナミクスから微視的に解明します。研究手法は主に計算機(高性能コンピュータ)による分子シミュレーションを用い、必要に応じて情報科学的手法も活用します。また、複雑な分子の世界を直観的に理解するために、VRを用いた生体分子の可視化ツールの開発も進めています。これらの研究を通じてソフトウェア開発や創薬方面への応用を目指します。
組み合わせ問題に関する複雑さの調査およびそれらのアルゴリズムに関する研究
理論計算機科学はアルゴリズム理論を中心としたコンピュータサイエンスの1分野です。コンピュータ自身が研究対象であり、「コンピュータって何ができるんだろう?そして、コンピュータにできないことってどんなことなんだろう?」という素朴な疑問を追及する学問分野と言えます。本研究室では、特に計算量理論とその応用に関する研究を中心に行っています。
情報システムの設計と開発
情報システムとは、人々の社会活動を支える仕組みです。人工知能、画像処理,データ構造とアルゴリズムなどの計算機科学の知識を活かし、社会や組織の課題を解決する情報システムの設計・開発に取り組んでいます。自らの置かれた環境で、興味深い課題を見出し、自分が設計した情報システムを実現できるエンジニアを目指します。研究では個別一回性の強い情報システムになるので、定量的評価に加え,質的評価も重視しています。
ソフトウェアによるネットワーク通信の高速化
今日、SDNやNFVなどの仮想化技術により,複雑で高品質なサービスが提供されています.それに伴い,ソフトウェアでの高速なパケット通信が求められるようになっています.しかし一方で,大規模,巧妙化するサイバー攻撃に対するネットワークセキュリティが重要視されています.そこで,安全性を維持しながらより高速にパケット通信を行うためのネットワークセキュリティシステムの開発を目指しています.
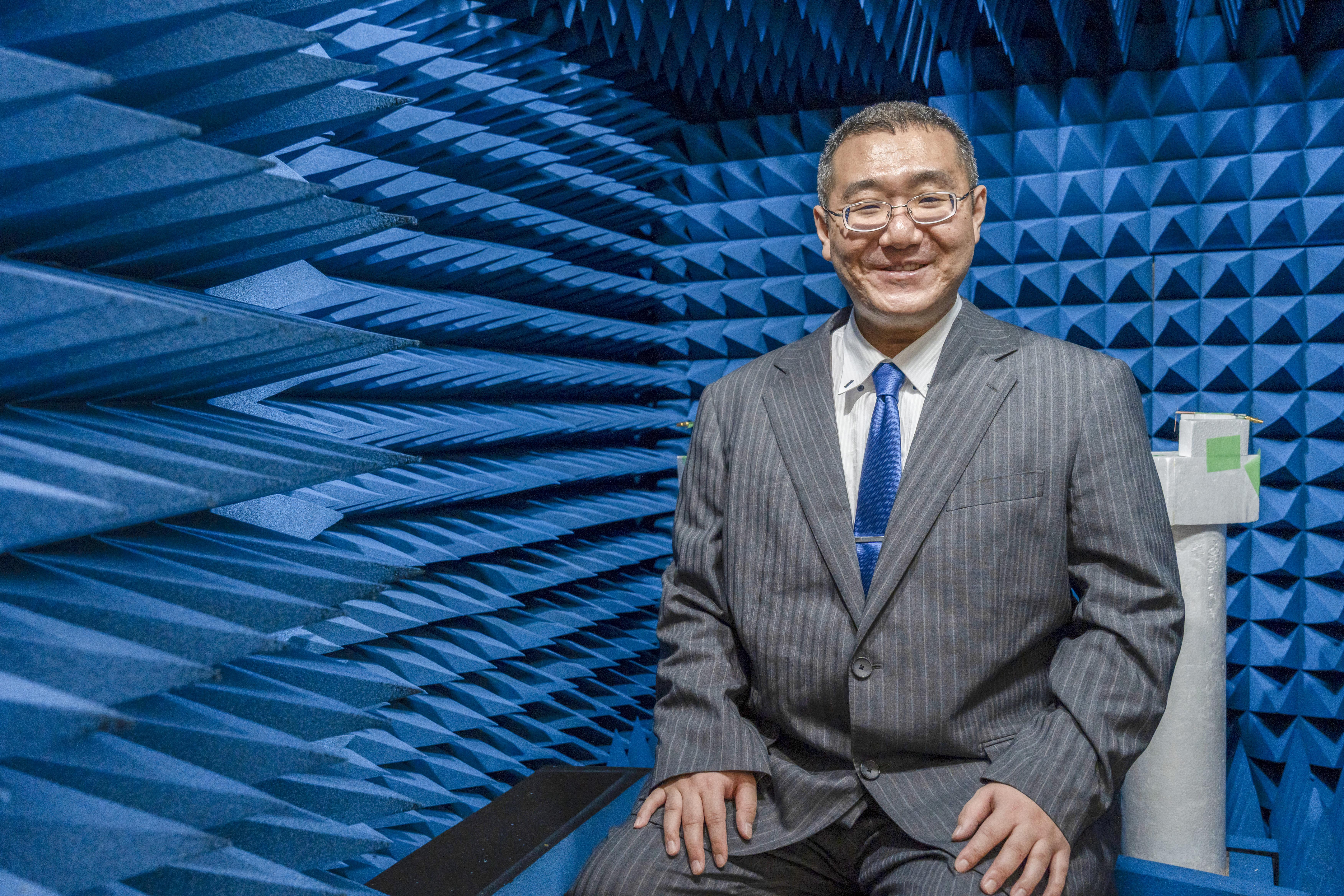
あらゆるモノがインターネットでつながる時代に必要なアンテナの実現に関する研究
電磁波工学研究室では、身近なスマホや医療デバイスに使われる「見えない電波に関する技術」を、自ら設計・製作・測定しながら研究できる実践型の環境を整えています。教科書に載っている基本的なアンテナから導電性繊維による最新ウェアラブル技術まで、手を動かして理解できるのが強みです。将来は、安心・安全でワイヤレスが当たり前の社会を、あなたの技術で支えるエンジニアへと成長することを目指します。
赤外線分光カメラ撮像データの解析
リモートセンシング装置を開発して人工衛星や惑星探査機に搭載し、対象の遠隔観測を行って科学成果を挙げます。近年では、小惑星探査機はやぶさ2に搭載した中間赤外カメラTIRをJAXAと共同で開発して、小惑星リュウグウを観測して地球の水や生命誕生の秘密を探るためのデータを取得しました。さらに、TIRの後継機であるTIRIを二重小惑星探査機Heraに搭載して、小惑星DidymosとDimorphos系の探査を行う予定です。開発した赤外分光カメラを惑星探査だけでなく、医療に活用できないか、模索しています。
生体信号による感情推定
・自然現象や室内音響等のコンピュ-タ-・シミュレ-ションによる研究 ・生体信号を用いた感情推定 ・人間の感覚と感情の関係について ・コンピュテーショナル・デザイン ・AIの応用
天然変性領域中の機能部位予測プログラムの開発
現代社会では情報処理技術や生物工学技術などの発達に伴い、ビッグデータと呼ばれる大量のデータが蓄積されています。これらのデータに対し機械学習などの情報解析技術を用いた解析を行うことで、新たな知見の獲得や予測モデルの開発を行い、人間の思考・決断の助けになるような技術の開発を目指しています。現在はタンパク質の機能に関わる領域を予測する機械学習モデルの開発に加えて、ドローンを用いた農業やスポーツにおけるデータの収集・解析など生命科学に限定せず幅広い分野に解析対象を広げています。
タンパク質やゲノムデータの計算機による解析
タンパク質の構造やゲノム情報を情報学の手法を用いて解析しています.特に,天然変性タンパク質に関する研究を長年続けてきました.タンパク質はアミノ酸が数十から数百繋がった紐状の分子で,この紐状の分子は立体的に折り畳まれ構造を形成することで機能を発揮します.しかし,天然変性タンパク質は、紐状のまま存在しなおかつ機能を有しています.タンパク質構造の計算機による解析では,前世紀の末からAIを用いた研究が行われており,本研究室でもAIを用いた天然変性領域予測の研究を行なっています.
遺伝的プログラミングによる振動生化学反応系の状態方程式の推定
生成AIはヒトの脳の仕組みをコンピュータで再現する研究から発展してきました。私の研究室では、生き物が持つ高度な情報処理の仕組みについて調べ、工学への応用を目指しています。そのためのコンピュータシミュレーションに必要な数理モデルの作成と数値解法の考案を行っています。また、グラフィックスボードを利用した数値解法の並列化と高速化、コンピュータシミュレーションを容易に行うためのアプリの開発を行っています。
音声・画像・通信・生体の適応信号処理・機械学習の基礎理論とその応用の研究
主な研究内容は大別して、二つのテーマで研究を行っています。一つは信号処理の一分野である情報推定及び抽出の理論とその応用に関する研究です。二つ目のテーマは、ICT技術に基づく情報メディアネットワークの構築とこれを利用して新しい地域文化や産業構造を構築する研究を行っています。
植物のオミックスデータを中心とするビッグデータの解析
オミックス(Omics、オーミクス)は、「すべて」などを意味するomeに「学問」を意味するicsを合成した造語で、膨大な生物学的情報から相互作用や機能を解析する分野です。特に植物や環境データに注目しており、生物と環境の相互作用を理解することで、農業への応用や環境保護への貢献を目指します。
セキュリティを考慮した情報システムの開発
パズルのような組合せ数学問題からセキュリティを考慮したネットワークシステムの設計まで、幅の広いテーマを研究しています。「アルゴリズム」と「セキュリティ」がキーワードです。組合せ数学問題を解くアルゴリズムは、セキュリティ技術の開発に応用され、セキュリティ技術はネットワークシステムの設計に役立てられます。研究室では、セキュリティを意識した技術開発を目指しています。
- 1