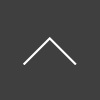本学は、建築・都市・環境工学群、情報・生命工学群の2学群から構成される、工学部単科大学である。大学として、入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)、教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)の3ポリシーを定めている。多様な特色をもつ2学群では、それにしたがい、学群の理念を実現するため、さらに学群ごとに3つのポリシーが定められている。
・教育課程編成・実施の方針をもとに学び、成長するために必要な、高校課程の基礎的な学力を備えている人 ・工学に関心を持ち、みずから考え、判断する力を育くみ、何事にも積極的に挑戦しようと 考えている人
・発想力、洞察力、コミュニケーション力をみがくため、持続力をもって学ぼうとする人
・対話によって気づきを共有することが、学びを深めるために大切だと認識する人
・卒業認定・学位授与の方針を達成するために必要な、教養基礎科目、専門教育科目を学修する
・工学教育を特徴づける実験・実習・演習をとおして、課題の解決に必要な知識と方法を修得し、その結果を論理的に発表する力を身に付ける
・本学での学修に加え、インターンシップなどの学外活動をとおした実社会との交流も促進し、表現力、協調性、倫理性を涵養する
・本学がめざす自然と人との共生、持続可能な循環型社会の構築に寄与するための幅広い基礎的な学力、工学の知識と技能を修得し、判断力と実行力を有している
・自ら課題を見いだすことができ、解決に主体的に取り組み、その成果を発表する能力を備えている
・他者との協働に参画し得る社会性を有し、専門技術者として果たすべき使命と役割を理解し、倫理観や責任感を身に付けている
身のまわりのアイテム、建築物、橋のような公共構造物と、それらとふれあう場としての生活空間・情報空間について、工学的にデザインする技術者の育成を目指します。日ごろ目にするも のやその環境が学びの対象です。持続的社会の構築を目指してどのように'もの'や'空間'と向 き合い、環境を整えるべきか、工学を手掛かりに考えたい人の入学を希望します。
広い視野と洞察力、独創的な発想力と問題解決能力、コミュニケーション力などの基盤となる数学・理科・国語・英語、特に数学・理科の基礎的学力を評価します。また学びを深めようとする意欲を確認します。高等学校等での習得すべき科目は、数学では数学I・II・III・A・B・C(あるいは同等の科目)、理科では、物理(物理基礎を含む)・化学(化学基礎を含む)、国語、英語及び情報Ⅰで、入学時までにこれらの科目の内容を理解していることが望まれます。
学群のディプロマ・ポリシーを達成するために、教養基礎科目、専門教育科目(工学基礎科目、学群共通科目、プログラム専門科目)に分けて、次のとおり年次進行で学修する。
初年次は、幅広い学友とともに教養基礎科目を学び、豊かな人間性を身に付け、文理融合型学修を実践すると同時に、工学基礎科目及び学群共通科目の履修により、工学技術者としての最低限必要な基礎学力を身に付ける。
2年次においては、学群共通科目の履修をとおして学群の関係する広範な学術分野を横断的に理解できる能力を開発するとともに、それぞれの教育プログラムの基礎的な科目を学び、学生ひと ひとりが基礎知識と自己表現力・提案力を身に付け、自らの志向、能力、個性を見いだしていく。
3年次においては、それぞれの教育プログラムの専門科目を中心に学び、専門的知識を獲得し、それを応用する力を養う。
4年次においては、専任教員の研究室に所属し、専門技術者に必要な知識、知恵を修得しつつ、卒業研究に取り組むことで、論文のまとめ方、プレゼンテーションの方法、討議の仕方を学び、大学教 育の総仕上げを行う。
所定の年限在学し、所定の授業科目を履修して、卒業に必要な130単位以上を修得し、次の能力を有すると認められた者に学士(工学)の学位を授与する。
自ら問題を発見し、論理的に分析し、解決する能力を身に付け、そしてその結果を、市民を含めた第三者に対して、分かりやすく伝達することができる。
学んだ技術や知識をもとに、状況に応じて柔軟に対応できる応用力を身に付けている。
人間の生活の豊かさ、人間の健康、地球の環境のために、必要な情報や基礎知識を抽出して活用しつつ、問題を創造的に解決することができる。
自然と人との共生や持続可能な循環型社会の構築に貢献するために、様々な専門職業人と協働するコミュニケーション能力を身に付けている。
情報科学・生命科学・ロボット技術と、微生物から人間まで様々な生きもののもつ優れた機能の利用によって、よりよい社会をつくる技術者の育成を目指します。データサイエンスおよびラ イフサイエンスがおもな学びの対象です。最先端の技術を持続的社会の形成に役立て、人々の暮 らしを豊かにする方法を考えたい人の入学を希望します。
広い視野を持って、自然科学・工学の知識を収集・理解し、問題を発見、分析、解決するための基盤となる数学・理科・国語・英語、特に数学・理科の基礎的学力を評価します。また学びを深めようとする意欲を確認します。高等学校等での習得すべき科目は、数学では数学I・II・III・A・B・C(あるいは同等の科目)、理科では物理(物理基礎を含む)・化学(化学基礎を含む)、生物(生物基礎を含む)(あるいは同等の科目)、国語、英語及び情報Ⅰで、入学時までにこれらの科目の内容を理解していることが望まれます。
学群のディプロマ・ポリシーを達成するために、教養基礎科目、専門教育科目(工学基礎科目、学群共通科目、プログラム専門科目)に分けて、次のとおり年次進行で学修する。
初年次は、幅広い学友とともに教養基礎科目を学び、豊かな人間性を身に付け、文理融合型学修を実践すると同時に、工学基礎科目及び学群共通科目の履修により、工学技術者としての最低限必要な基礎学力を身に付ける。
2年次においては、学群共通科目及びそれぞれの教育プログラムの基礎的な科目を履修し、学生ひとりひとりが技術者としての基本的な素養とともに情報工学及び生命工学に関する基礎知識を身に付け、自らの志向、能力、個性を見いだしていく。
3年次においては、それぞれの教育プログラムの専門科目を中心に学び、専門的知識を獲得し、それを応用する力を養う。
4年次においては、専任教員の研究室に所属し、専門技術者に必要な知識、知恵を修得しつつ、卒業研究に取り組むことで、論文のまとめ方、プレゼンテーションの方法、討議の仕方を学び、大学教育の総仕上げを行う。
所定の年限在学し、所定の授業科目を履修して、卒業に必要な130単位以上を修得し、次の能力を有すると認められた者に学士(工学)の学位を授与する。