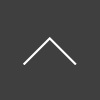前橋工科大学では、本学の教育・研究に触れることで、興味・関心をもっていただき、進路選択の一助となるよう、出張講義を行っております。
※高大連携を希望される学校の自主性を尊重したいため、受験産業等の業者を介したお申込みは、原則としてご遠慮ください。
※土日祝祭日実施の出張講義は受付しておりませんので、あらかじめご了承ください。
※本学の業務日程や教員の都合などによりご希望に添えないこともございます。ご了解ください。
高校生を対象としています。
(1)出張講義一覧よりご希望の講義名・講師を検討し、申込書に必要事項を記入の上、下記問い合わ
せ先までお申し込みください。
(2)内容を確認次第、担当者より連絡させていただきます。
なお、ファックス・email送信日から1週間たっても連絡がない場合(土日祝祭日を除く)は、
お手数ですが、学務課入試係までお電話いただきますようにお願いします。
問い合わせ先:学務課入試係 TEL:027-265-7361
送付先 FAX:027-265-3837 メール:nyushi@maebashi-it.ac.jp
令和6年度出張講義一覧(学群・専門分野・講師名等も記載されております)
| № | 講義名 | 内容 | 職名 | 講師名 |
| 1 | 液状化のおもちゃ'エッキー'を もとにした土木工学の紹介 |
液状化現象とそれに起因した地震被害および液状化対策工法について紹介します。また、土木工学は社会に役立つ技術を対象としていることを説明します。 | 教授 | 土倉 泰 |
| 2 | 水のきれいさ・汚さ | 日常生活で使用している水はどこから?そしてどこへ? 上下水道技術や水循環システムなどの来し方行く末について一緒に考えましょう。 | 教授 | 田中 恒夫 |
| 3 | 環境にやさしいまちづくり・災害に強いまちづくり | 安心して暮らすことのできる群馬のまちづくりを目指して、環境への影響が小さく、災害に強いまちを作っていくためのヒントについて解説します。 | 教授 | 森田 哲夫 |
| 4 | 水や空気の流れの不思議 | 飛行機はなぜ飛ぶのか、無回転シュートはなぜ揺れるのか、津波はなぜ怖いのか、などの流体運動に関して多くの具体的な疑問を投げかける。 | 准教授 | 梅津 剛 |
| 5 | 日頃使っているコンクリートの建物はどのくらい長持ちする -強いから長持ちするわけではない?- |
鉄筋コンクリート製の建物を我々は毎日安心して使っています。でも、橋やトンネル、マンションやオフィスビル、学校の校舎も、永久に使えるわけではありません。いつの日か必ず劣化して使えなくなります。なぜ劣化するのか?劣化するとどうなるのか?どう造れば長持ちさせられるのか?解説します。 | 准教授 | 舌間 孝一郎 |
| 6 | 超身近な、実はエコでナノテクのコンクリートのはなし | 家庭のゴミがコンクリートになったり、一見ローテク?実はナノテク、など身近だが意外に知られていないコンクリートについて解説します。 | 准教授 | 佐川 孝広 |
| 7 | 河川の環境と防災 | 都市を流れる河川水辺環境の問題とその対策、ならびに集中豪雨等による水災害の問題とその対策について講義します。 | 准教授 | 平川 隆一 |
| 8 | 自分の家は災害に強いのか?~地図から災害安全性を見分けるコツ教えます~ | 自然災害が増加している今日この頃。誰しも安全な場所を知りたいですよね。実は、地図を読み解くと、災害に強い場所・弱い場所がわかるのです。そのコツを伝授します。 | 准教授 | 森 友宏 |
| 9 | 将来の自分のやりたいこと・進路は、どうやって決めたら良いの?~土木工学・建築学を例として~ | 昨今、職業の形態が多様化してきており、自分が何をやりたいか分からないまま進路を決めてしまう学生が増えていますが、進路選択は将来の職業選択・生活スタイルに直結する重要な問題です。近年の大学生の進路指導および就職後の追跡調査結果をもとに、高校生が進路を決定する時のタブー、学生自身がやりたいことを自己分析する方法、興味のある分野の分野研究の方法などをアドバイスします。 | 准教授 | 森 友宏 |
| 10 | 見えない力を見る技術 ~壊れないモノを作るため、 壊して分かる技術と壊さなくても分かる技術を知ろう~ |
壊れないモノを作るためには、壊すことで学ぶ学問として破壊力学があります。 モノに力を加えたとき、モノが耐えている力を見るための技術を紹介します。 |
准教授 | 宮川 睦巳 |
| 11 | クレーン作業入門 | 建設現場や工場で使用されるクレーンについて重要性とそれに付随する資格をお話します。 | 講師 | 山中憲行 |
| 12 | 建築の空間と光 | 古今東西の著名な建築を紹介し、空間と光の関係について説明します。光の役割とその効果について一緒に考えていきます。 | 教授 | 若松 均 |
| 13 | 自分を知る・世界を知る -巣作りとしての住まいー |
私たちは食(ご飯)によって体(皮膚)をつくり、衣(衣服)によって暑さ寒さに対応する事から、住(建物)を三番目の皮膚と考えます。動物としての人間も巣としての住まいが必要なのです。 | 教授 | 石川 恒夫 |
| 14 | 木の建物 | 日本は豊かな森林資源をもっています。法隆寺は世界屈指の木の建物です。これから皆さんが暮らす街や住まいはどのような建物が望ましいのでしょうか。木の建物について考えてみましょう | 教授 | 石川 恒夫 |
| 15 | 建築をデザインすること | 建築家は何を考え何を実現しているのか。講師が実際にデザインした住宅や集合住宅の実例を通して解説します。 | 教授 | 駒田 剛司 |
| 16 | 建築と耐震構造-地震に強い建物をつくる技術- | 建築がどの様に発展してきたかについて、力学的観点からわかりやすく解説をします。また、地震多発国である日本における最先端の耐震技術についても紹介します。 | 教授 | 北野 敦則 |
| 17 | 建物の耐震化はなぜ必要? ~建物の倒壊・損壊から命や財産を守る~ |
これまで大きな地震が発生した際に、建物にどんな被害が生じ、そしてどんな風に人命が失われたのかについて振り返りながら、そのような被害を繰り返さないためにすべき対策について話します。 | 教授 | 麻里 哲広 |
| 18 | 住まいを長持ちさせるために必要なこと | 住宅の長寿命に不可欠な要素の整理と住民が行うべき作業をハード・ソフトの両面から解説します。 | 准教授 | 堤 洋樹 |
| 19 | 公共施設を使い「まち」を変える | 既存の公共施設を有効活用し「まち」の活性化を目指すために求められる活動を事例を踏まえて解説します。 | 准教授 | 堤 洋樹 |
| 20 | まちの姿から見た空き家問題 | 空き家の実態調査を基に空き家問題が発生する仕組みから空き家の利活用に求められる要件を解説します。 | 准教授 | 堤 洋樹 |
| 21 | 省エネで快適な住宅 "ZEH(ゼッチ)"とは? |
ZEH(Zero Energy House)とは、「快適な室内環境」と「年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下」を同時に実現する住宅です。講義では、ZEHがなぜ必要なのか?また、実際のZEH住宅の事例を紹介します。 | 准教授 | 三田村 輝章 |
| 22 | 室内空気を清浄に保つアレルギー対策住宅とは? | ぜんそくや花粉症などのアレルギー疾患は増加傾向にあり、住環境が影響しているとも言われています。本講義では、住環境とアレルギー疾患の関係について解説し、アレルギー対策住宅の開発事例を紹介します。 | 准教授 | 三田村 輝章 |
| 23 | 都市計画・まちづくりにおける計画支援技術 | 安全で暮らしやすい、持続可能な都市やまちをつくるための考え方を解説します。また、その計画のための技術の一例(AI、ビッグデータ、GISなど)を紹介します。 | 准教授 | 辛島 一樹 |
| 24 | 建築構造とサスティナビリティ | 「持続可能な社会」の実現が求められています。建築分野において考えやすい世界共通の開発目標として、例えば「住み続けられるまちづくり」などが挙げられます。一方日本は、地球人口が急増している中で少子高齢化を伴う人口減に直面している国でもあります。世界的な課題・日本ならではの課題の双方に、構造工学の分野から貢献できることについて紹介します。 | 准教授 | 佐藤 良介 |
| 25 | 建築で音を操る | 音は目に見えませんが、空間の快適性に大きく影響します。快適な音環境を実現するための建築設計や技術、研究事例について紹介します。 | 准教授 | 米村 美紀 |
| 26 | 都市デザインの視座 | 「都市デザイン」とは何を対象にどんなことを考えながら行なうデザイン分野なのかについて、事例をまじえて解説します。 | 講師 | 稲見 成能 |
| 27 | 電気自動車のデザイン | 自動車の動力が、内燃機関から電動モーターに急速に転換している。電気自動車はどんな形になるのか?どんな使い方が予想されるのか?プロダクトデザインの観点を紹介します。 | 教授 | 江本 聞夫 |
| 28 | 共振の話 | 共振(共鳴)という物理現象について、具体的な例を基に説明をします。また、身近にあるもので、共振を利用しているものについてもお話をします。 | 准教授 | 伊佐 浩史 |
| 29 | 「風景を建築する」とは?ランドスケープ•アーキテクチュア序論 | ランドスケープ•アーキテクチュアとは、どのようなデザイン分野なのかを紹介します。その成立過程として、環境との関係において人が生存の場を獲得し、近代都市の発展に至るまでとを概観します。 | 准教授 | 杉浦 榮 |
| 30 | 建築や空間をデザインするときに考えていること | 世界で一つしかない建築や空間がどのようにつくられるか。物体として見えるところだけではなく、人間の生活を支える空間として、また周辺環境を考慮した巨視的視点から、更にスケールやプロポーションなどの人間の感覚に関わることをトータルに検討しながらすすめるデザインについてお話します。 | 准教授 | 石黒 由紀 |
| 31 | クリエイティブコーディング入門 | 「クリエイティブコーディング」とはプログラミングによって創造的な表現を生みだす行為です。実際にプログラミングしながら創作していきます。 | 准教授 | 田所 淳 |
| 32 | 木材を五感でデザインする | 木材は私たちの生活環境の中で当たり前のように用いられています。ではなぜ、これほどにも多く使われているのでしょうか?その魅力を事例を紹介するとともにデザインの観点から五感を使った体験をしていただきます。 | 講師 | 中島 修 |
| 33 | 前前前世から学ぶ空間デザインの仕事 | 空間デザインの魅力は、連綿と続くその歴史にもあると言えるでしょう。19世紀まで遡って、デザインの役割について一緒に考えてみます。 | 准教授 | 臼井 敬太郎 |
| 34 | 批評性をもってニューメディアをみつめるまなざし | 人類史はニューメディアの発明と普及の歴史でもあります。ニューメディアは生活に利便性をもたらし、人間の認識領域を拡張して新たな知的フロンティアを創出する可能性を秘めた存在ですが、ときに瞞着や抗争の手段となり、格差を助長するツールとなることもあります。わたくしたちやその子孫が文化的繁栄を続けるために、現代において社会インフラとして機能しつつあるSNSや仮装通貨などのニューメディアとどのように向き合えば良いのか? ともに考えましょう。 | 助教 | 阿部 由布子 |
| 35 | ヒトに寄り添ったデザインを考える | 世間一般とデザイナーとで捉え方にギャップのある「デザイン」に関して、デザイン史を概説することで、デザインについての認識を共有します。その後、ヒトの認知処理に関する知見を紹介し、ヒトに寄り添ったデザインに必要な要素を解説します。 | 講師 | 赤間 章英 |
| 36 | SDGsで考える環境とDNA | 副作用の少ない薬の開発、がん研究など、病気との結びつきの強いDNA情報ですが、環境分野においても重要なデータを提供します。DNAとは何かから、どんな未来が待っているか、一緒に考えます。 | 教授 | 蒔田 由布子 |
| 37 | 進化のはなし | 生物はどのようにして現在のような多様な姿になったのか。遠い昔に起きたことを今得られる情報から推定する方法について紹介します。 | 教授 | 中村 建介 |
| 38 | コンピュータで生物を探る | 近年の生物学では様々な場面でコンピュータが利用されています。生物学の研究にどのようにコンピュータや情報技術が活用されているかを紹介します。 | 教授 | 福地 佐斗志 |
| 39 | 安全なパスワードの作り方~パスワードの数理科学 | インターネットサービスでは、ユーザIDとパスワードで個人を認証していますが、どのようなパスワードが安全でしょうか。技術的な限界と対策を解説します。 | 教授 | 三河 賢治 |
| 40 | インターネット社会を支える暗号技術 | インターネット上で私たちの大切な情報を守るために、暗号の技術が用いられています。本講義では、現代暗号のしくみについて、分かりやすく紹介します。 | 准教授 | 遠山 宏明 |
| 41 | AIで"なに"ができる? 〜生命科学編〜 |
AIを生命科学に応用すると何ができるのでしょうか。近年の生命科学におけるAIの活躍や限界を実際の例を交えて紹介します。 | 助教 | 安保 勲人 |
| 42 | インターネットの身近な危険 | 皆さんが何気なく使っているパソコンやスマートフォンがどのようにネットワーク通信を行なっているかと,その危険性及び対策について紹介します. | 助教 | 渕野 敬 |
| 43 | 光で探るあなたの健康 | 光には様々な性質があり、例えば虹のように色として認識できる光から目には見えない光もある。光を用いてからだを計測する方法は医療だけでなく普段の生活にも生かされている。その計測の仕組みをいくつか紹介します。 | 教授 | 野村 保友 |
| 44 | 人間を支援するロボットシステム | 人の力信号や筋肉から生じる電気信号などを利用した福祉介護ロボットをご紹介します。 また、研究室で開発した移動型アシストロボット、人が装着できる外骨格ロボットの体験・デモを行うことも可能です。 |
助教 | 李 沛譲 |
| 45 | 音とスマホの秘密の話 | 身近な音とスマホについて工学の視点から、音の発生する仕組み、人と動物の声と耳、通信における音声、スマホの正体と音声処理などをテーマに解説する。 | 教授 | 松本 浩樹 |
| 46 | 我々の体と電気 | 生体内の電気活動、心電図、脳波の基本知識を解説します。 | 教授 | 王 鋒 |
| 47 | 人間の体の仕組みと病気の治療 | 人体の正常機能構造とは、その異常説いての病気、これら近代医学に欠かせない医工学について概説 | 教授 | 首藤文洋 |
| 48 | ヒトの"こころ"に寄り添ったものづくり | 目まぐるしい技術発展の中でヒトの心に寄り添ったインターフェース開発は重要である。生理学的人体や神経の理解から客観的なユーザビリティーを評価する取組を解説する。 | 教授 | 首藤文洋 |
| 49 | 感覚・脳・行動の科学 | 行動はどのようなしくみによって生み出されるのだろうか。動物行動の見方から神経系のはたらき、さらに生物機能を利用したものづくりについて解説します。昆虫(カイコガ)を用いた行動実験の実施も可能です。 | 准教授 | 安藤 規泰 |
| 50 | 脳機能の計測方法について | ヒトの脳機能の計測方法について講義します。脳波やfMRIなどの計測原理、経頭蓋磁気刺激法を用いた脳機能計測を紹介します。 | 准教授 | 小田垣 雅人 |
| 51 | はやぶさ2の科学探査 | 小惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウを探査して、地球にサンプルを持ち帰りました。どんな発見があったのでしょう?はやぶさ2の科学探査について詳しく解説します。 | 准教授 | 荒井 武彦 |
| 52 | 電波とアンテナの仕組み | 身の回りで通信に使われる電波とはどのようなものなのか講義します。また、電波の出入り口であるアンテナに隠された工夫と謎について紹介します。 | 助教 | 藤田 佳祐 |
| 53 | ゲノムと遺伝子 | 遺伝情報全体である「ゲノム情報」について解説し、その活用事例を紹介します。 | 教授 | 善野 修平 |
| 54 | 遺伝子を調べてがんを治す | 最新のがん治療では、それぞれの患者さんのがん細胞の遺伝子を調べて、その結果に応じて薬や治療法を選択することが行われています。それは分析技術の途轍もない進歩により実現しました。その仕組みを紹介します。 | 教授 | 山下 聡 |
| 55 | お酒を作る微生物酵母の力 | 様々なお酒の作り方、お酒を作る微生物、酵母の役割を解説します。 | 教授 | 尾形 智夫 |
| 56 | 植物ホルモンのはたらきとその利用 | 「植物ホルモン」について、その発見の歴史から最近の研究結果までをわかりやすく解説します。さらに、実際の利用方法なども紹介します。 | 教授 | 本多 一郎 |
| 57 | お茶について〜栽培から効能まで | 知っているようで知らないお茶について、お茶の樹の栽培、お茶の効能など様々な話題を紹介します。 | 教授 | 本間 知夫 |
| 58 | 電気的な方法で生物の働きを調べる | 生物(動物・植物)の働きを電気的に調べる方法とその利用例について紹介します。 | 教授 | 本間 知夫 |
| 59 | 腸のサイエンス | 消化・吸収の場である腸について、その働きを調べる方法や利用例を紹介します。 | 教授 | 本間 知夫 |
| 60 | センシングと健康管理 | センサーを用いることで生体内に存在するバイオマーカ-を測定し疾病の予防と健康管理について解説します。 | 教授 | 菅原 一晴 |
| 61 | 環境と健康に関わる微生物 | 私たちの生活に非常に重要である微生物についてわかりやすく解説します。 | 准教授 | 林 秀謙 |
| 62 | 糖鎖の化学について | 感染からガンに至る、甘くない糖鎖が体の中でどのような働きを果たしているのかについてお話します。 | 准教授 | 星 淡子 |
| 63 | 食品の機能とその応用 | 「食品」の持つ様々な機能について解説するとともに、病気の予防を目指した機能性食品への応用例について紹介します。 | 准教授 | 薩 秀夫 |
| 64 | 脳の不思議 | 人体の中で最も謎に包まれている脳。なかでも記憶がどのようにして形成されるのか未だ解明されていません。講義ではその記憶形成メカニズムにフォーカスをあてたい。 | 准教授 | 石川 保幸 |
| 65 | 植物のバイオテクノロジー | 植物への遺伝子導入技術について、それらの特徴を解説します。また、遺伝子組換え作物の作成法や実例、さらにそれらをとりまく環境についても紹介します。 | 准教授 | 中山 明 |