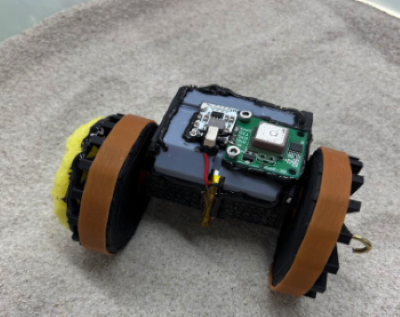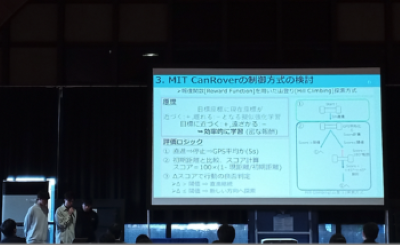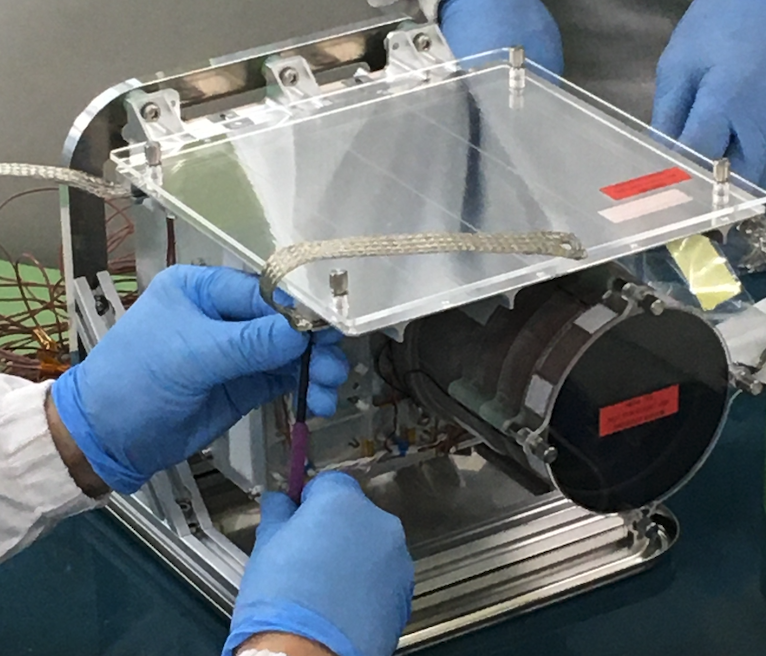日 時 : 2024 年12 月5 日(木)13 時00 分~14 時20 分
場 所 : 前橋工科大学工学部131 講義室(群馬県前橋市上佐鳥町460-1)
演 題 : 移動の自由を実現する福祉車両の開発
講 師 : 佐藤 勝彦 氏(株式会社ミクニライフ&オート オート事業部)
主 催 : 電気学会東京支部群馬支所
共 催 : 前橋工科大学工学部生命工学領域
協 賛 : 特定非営利活動法人 Wireless Brain Network 研究会
参加人数 : 60 人(学生:54 人、教職員:5 人、一般:1人)
障がい者(主に車いす利用者)の移動手段となる福祉車両・公共交通機関についての講演であった。 福祉車両には、障がい者自身が運転することができる「自操式車両」と、介助・介護されることを目的とした「介護式車両」がある。車いす利用者の身体障害の程度、残存機能レベルによって必要とされる製品があり、利用者の声とともに紹介された。また、様々な障がいを持つ人の移動の自由を実現するための製品開発とその過程での苦労話があった。さらに、移動の自由の先にある社会貢献について解説があった。

講 師 : 佐藤 勝彦 氏(株式会社ミクニライフ&オート オート事業部)
株式会社ミクニライフ&オートの企業理念は、「全ての人に移動の自由を」である。1973 年の創業以来、「一人でも多くの方に運転する歓びを伝えたい」という想いのもと、身体の不自由な人向けの自動車運転装置をはじめとした福祉車両装置を主な事業として展開してきた。
自操式車両利用者の中でもっとも多い身体障害は、四肢の一部欠損や麻痺による機能不全である。一人一人の障害の程度に応じた運転補助装置を開発している。自操式車両への乗車が可能な対象者は、両下肢に障害があり、左右いずれかの足でアクセルペダル・ブレーキペダルを操作できない人である。そのために手動運転装置(商品名:AP ドライブ)を開発して、手動レバーにアクセル、ブレーキ、ウインカーそしてホーンの操作ができる機能を持たせている。健常者は通常どおりの運転ができ、家族などと共用できる。
片手でも旋回操作ができるようにステアリング旋回ノブ装着を提供している。対象者は手動運転装置を使用できる人、または上肢(腕または指)に障害がある人である。
常時車いすを使用していて上肢に障害または腕力が弱い人向けに、車いすを車両に収納する車いす収納装置を提供している。客の要望に沿うように取り付けをおこなっている。
介護式車両として「乗降補助装置」を製造している。常時車いすを使用している人や、杖などのサポートがあれば歩行可能な人が対象である。
車いす利用者の移動手段は、介護式車両と自操式車両そして公共交通機関である。介護式車両の利用者の感想は、疎外感、荷物になったような気分、乗車準備をしてくれた運転手に申し訳ない気分などである。公共交通機関の利用者の感想は、ラッシュ時でも車室内に広い空間を占有することで周囲の目線が気になる、乗車駅と下車駅との駅員間の連絡時間が加わることによる移動時間の増加、荷物の持ち運びに苦労、バスで乗車拒否をされた嫌な思いなどである。Door-to-door を考えれば、自操式車両のほうにメリットが多いと感じる肢体不自由者が多い。
福祉車両の開発において、AP ドライブに装備されているセコンダリコントロール機能は、車両のアナログ配線にコントローラを結線して得られる。近年はCAN(Controller Area Network)通信が採用されているため結線することが困難である。いずれにしても結線作業は大きなリスクを伴う。そこで、2026 年以降に新型Interface を開発する予定である。また、頚椎損傷C-5 レベルでAP ドライブのアクセル・ブレーキ操作ができない電動車いす利用者向けに、ジョイスティック運転装置(JOY カー)を開発した。
新たな取り組みとして、自動運転実証実験車両(マイクロバス、中型バス、水陸両用車)にジョイスティック運転補助装置の機構を転用して架装した。
社会貢献の実現に向けた取り組みとして、フォークリストやショベルカーなどの重機の遠隔操作技術を実現させることを目指している。肢体不自由者による遠隔操作が可能になり、新たな雇用が生まれる。
(特定非営利活動法人 Wireless Brain Network 研究会 岡田富男)