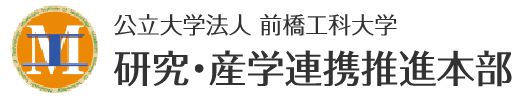地盤防災および地盤調査技術に関わる研究
地盤を土粒子一粒一粒のミクロの視点から見直すことによって,土粒子~水~空気の3相から成る「土・地盤」の物理・力学的特性を一から考え直します。これにより,大雨や地震の時に地盤災害が生じるメカニズムを明確に定義し,土砂災害発生までの余裕度や,地震時の液状化発生危険度などを定量的に示します。また,過去の自然災害事例を研究して地形ごとの危険度を分析したり,地盤の奥深くの調査技術の開発等も行っています。
主な研究成果
地盤を,土粒子ひと粒ひと粒のミクロの視点から見直すことにより,土の水分量に応じた不飽和土の強度を陽的に(順解法的に)算出する手法を開発しました。これまで,不飽和土の強度は現地の地盤サンプルを採取して強度試験を行うしか確認方法が無く,土の水分量に応じた不飽和土の強度は,多数の現地サンプルの強度試験から陰的に(陰解法的に)推定するしかありませんでした。開発した手法の研究を進めることで,不飽和地盤の水分に応じた強度変化の設計や,豪雨時の災害発生までの余裕度を定量的に算出することが可能となります。
また,住宅地盤における主要な地盤調査方法であるスクリューウェイト貫入試験(SWS試験)の幾何学的形状を詳細に分析することで,SWS試験の先端スクリューポイントの表面から地盤へと伝達される圧力を,世界で初めて定義・確認しました。これまで,SWS試験値(Wsw値,Nsw値)は物理単位が付与されていない無次元値でしかありませんでした。しかし,本研究成果によりSWS試験値と圧力が結び付けられたため,今後はSWS試験値を用いた,地盤の沈下量や液状化危険度の推定に関する研究が促進されることが期待されます。
どのような産学官連携ができるか
地盤防災に関わる技術開発・社会実装に関する連携が可能です。室内力学試験,模型地盤実験,実大実験など,
実際の土を用いた試験・実験が得意です。
【これまでに実施した産学連携の研究事例】
◆地形や造成履歴に応じた地震時の揺れやすさの面的分布に関する研究
◆簡易地震計を用いた住宅地盤の損傷度判定に関する研究
◆斜面における横ボーリング排水工と排水効果に関する研究
◆既存宅地擁壁の原位置補強方法に関する研究
◆住宅地盤の陥没被害に対するDIY補修方法に関する研究
SDGs該当番号